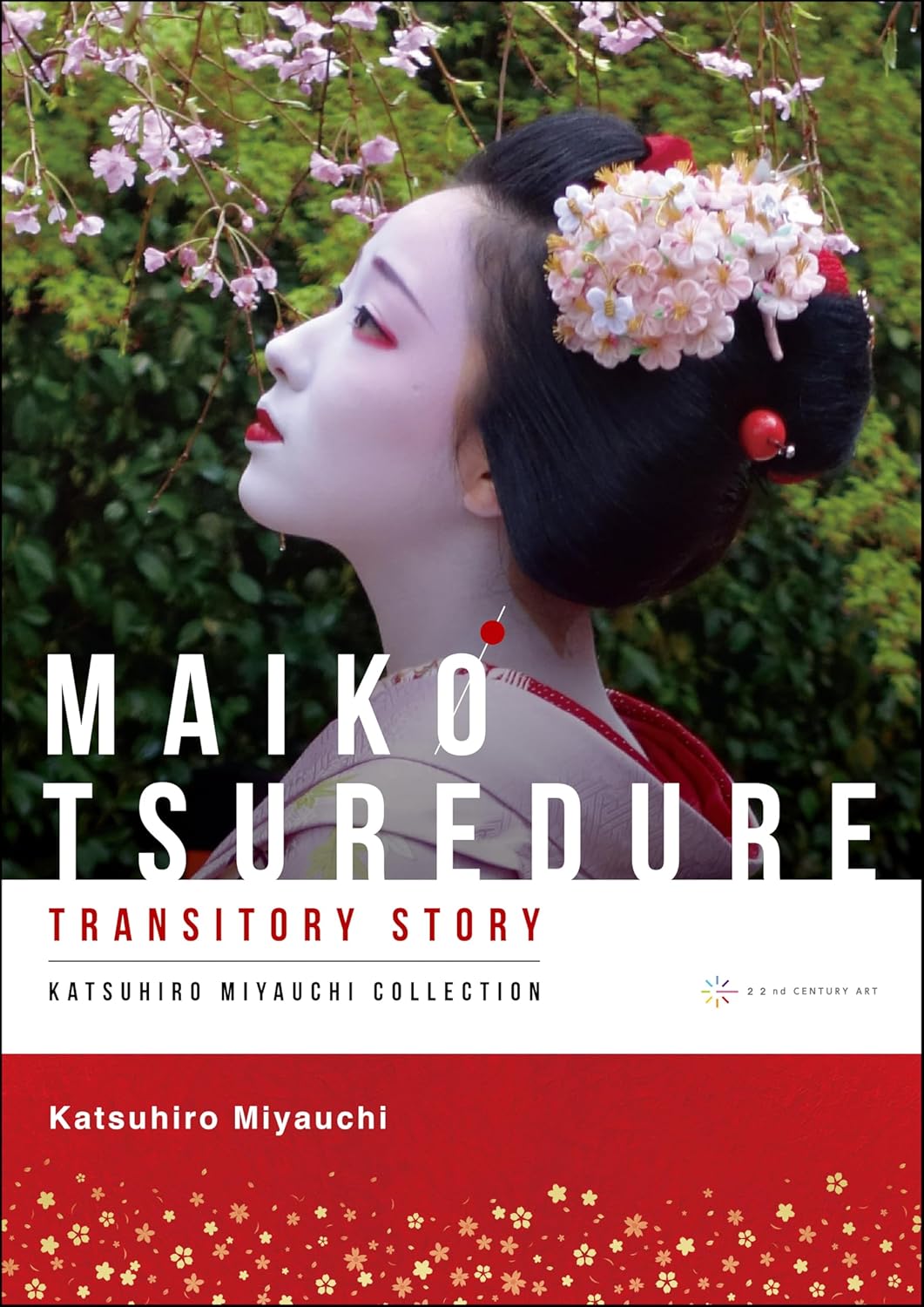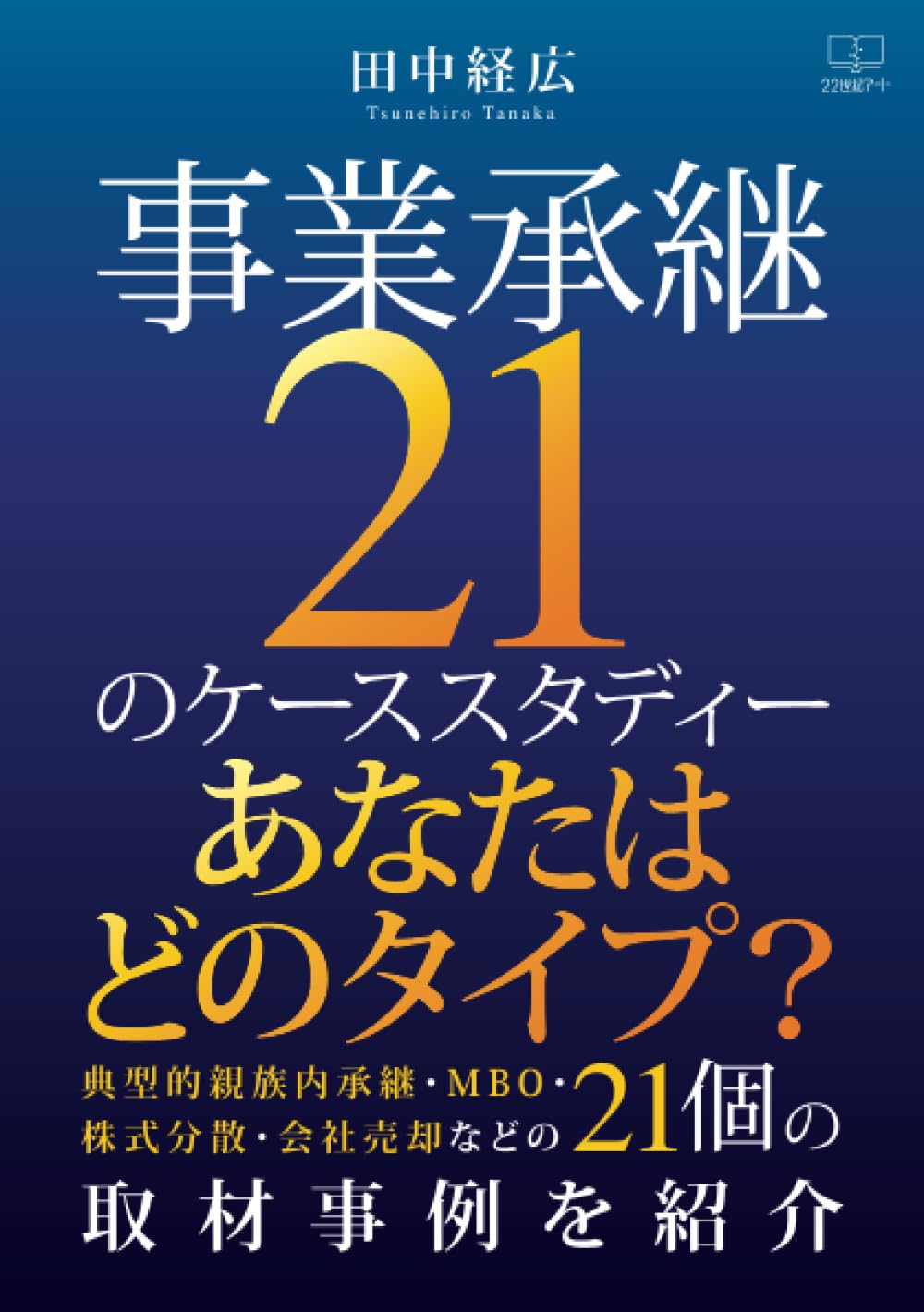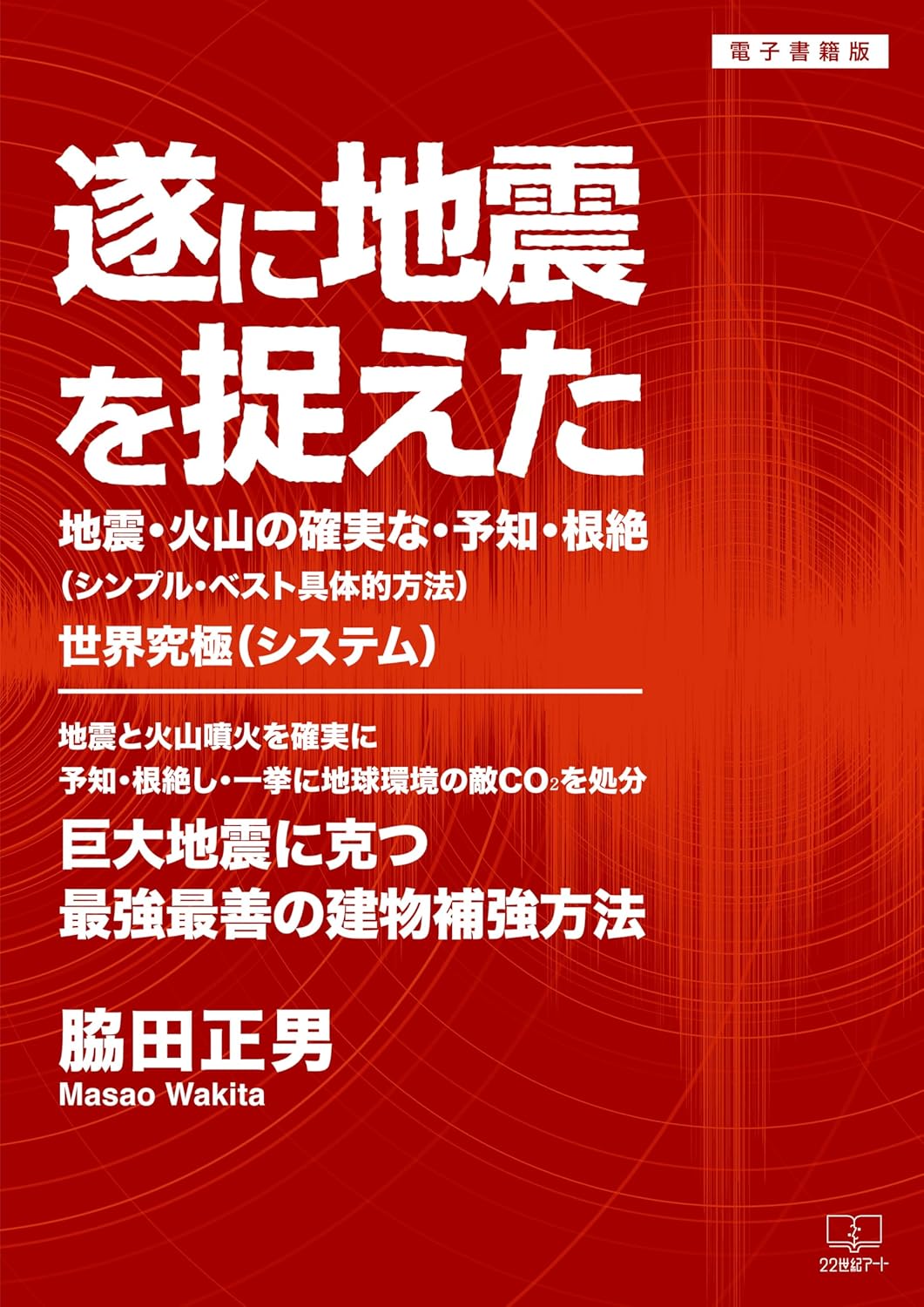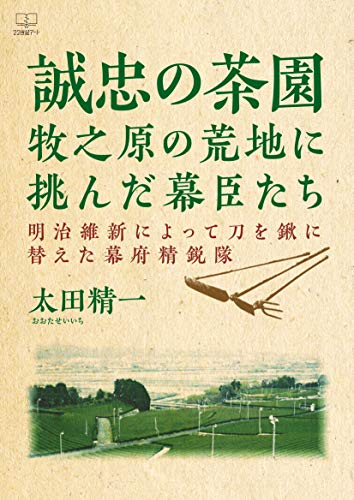
誠忠の茶園:牧之原の荒地に挑んだ幕臣たち 明治維新によって刀を鍬に替えた幕府精鋭隊
(著) 太田精一
Amazon作品詳細
爽やかな風が吹いている。新芽が出揃い、茶園は、若草色に染まっている。雲雀が、空高く舞い上がり、牧之原の灌木の茂みの中に消えて行った。
八十八夜も近い。
大草高重は、中條景昭と共に、牧之原の茶園を見廻っていた。
茶園は年々広がり、明治二十四年のこの年には、すでに茶処として全国的にも知られるようになっていた。
荒地として放置されて来た牧之原の大地は、旧幕臣たちの血と汗によって、開墾が進み、緑の茶園にその姿を変えつつあった。
だが、多くの同志が倒れ、離散し、入植当初の旧幕臣たちの数は、大幅に減少している。そのため、入植に至るまでの経緯とその後の開拓の歴史を知る者も少なくなった。
大草高重と中條景昭は、見廻りを進めながら、衰退する徳川家に忠誠を尽し、武士としての誇りを持ったまま刀を鍬に変え、二人三脚で茶園を築き上げて来た苦闘の歴史を振り返っていた。
二人は、初めて牧之原の視察に訪れた矢口原に、いつしか来ていた。
矢口原に立ったのは、明治二年の暑い夏であった。
眼下には大井川が流れ、東方には、富士の秀峰が手に取るように見えた。南には、駿河湾が真夏の陽を浴び、キラキラと光っていた。
灌木と雑草に覆われた坂道を喘ぎながら登って、やっと到達した矢口原の眺望は、前途に立ちはだかる困難を乗り越え、入植を決意させるほどの素晴らしいものであった。
手ごろな石を見つけ、休息のため二人は腰を下ろした。
高重は、二十年余りの苦難の歴史を刻んだ景昭の横顔に目をやった。その顔には、幕末の動乱の時代を生きぬいた証が、鐵の一本一本に刻まれている。
高重は、景昭の顔から目をそらし、じっと瞼を閉じた。すると幕府崩壊の予兆を招いた桜田門外の変のあった日から今日までの移り変わりが、走馬灯のように脳裏に浮かんでは消えて行った。(本文より)
【著者プロフィール】
太田 精一(おおた・せいいち)
東北大学文学部社会学科卒。
民間会社を経てジェトロに入る。カメルーン、旧ユーゴスラビア(現セルビア共和国)、チリに駐在。国内外の勤務を通して各国、各地方の歴史、文化を研究。市井の歴史家の集まり「史遊会」に所属。
数々のエッセイを執筆。同人誌「まんじ」の会員として小説や歴史物語を同誌に寄稿。
著書
『遥かなるカメルーン』(彩流社)
『遠い処へ』、『霧の彼方に』(まんじ特集号栄光出版社)
新刊情報